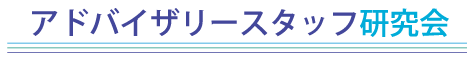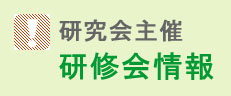研究会に寄せられたご意見・ご要望
―――――――――――――――――――――――――
会員様の声(update 2015.12.18)
―――――――――――――――――――――――――
![]() お願いですから一度研修会を開催してください。自助努力だと無資格者と同じになります。(kaeru)
お願いですから一度研修会を開催してください。自助努力だと無資格者と同じになります。(kaeru)
![]() 来春も、全国数会場での研修会を開催したいと計画しております。年明けには、詳細をご報告できるかと思います。
来春も、全国数会場での研修会を開催したいと計画しております。年明けには、詳細をご報告できるかと思います。
資格認定団体も、各地で研修会を実施しておりますので、当研究会の研修会のみならず、参加されるとよいかと思います。
また、皆様の地方公共団体で、健康食品をテーマとした市民講座等を企画されているところがあれば、講師派遣等は、ご協力させていただきますので、研究会事務局へご一報ください。
—————————-
![]() アドバイザリースタッフっていうものの、”一般の方への周知” (むうにいさん)
アドバイザリースタッフっていうものの、”一般の方への周知” (むうにいさん)
![]() 世間への認知を広めていただきたいと思います。(maimai)
世間への認知を広めていただきたいと思います。(maimai)
![]() アドバイザリースタッフについて、マスコミ等で周知が必要(tarorin)
アドバイザリースタッフについて、マスコミ等で周知が必要(tarorin)
![]() 資格者それぞれが努力していくことも必要かと思いますので、機会あるごとに消費者の方にPRお願いいたします。
資格者それぞれが努力していくことも必要かと思いますので、機会あるごとに消費者の方にPRお願いいたします。
本年12月に公表された食品安全委員会から消費者向けへの「健康食品」に関するメッセージでも、専門家としてアドバイザリースタッフが紹介されています。
ぜひ、皆さんからも、アドバイザリースタッフの認知向上に関して、所属の資格認定団体への働きかけをお願いいたします。
特に、マスコミへの露出は非常に効果があるものと思いますので、ご提案をいただければと思います。
—————————-
![]() よく言われていることですが、科学的根拠と安全性の情報は公開されても、一般の人々にはハードルが高すぎます。人間が利益やリスクを判断するのに論理的・総合的に判断するには高い負荷がかかるので、一面だけを見るなどヒューリスティック処理によって判断します。つまり機能性表示食品で公開されている情報はほとんどの人は面倒くさくて、見たくないということです。これからアドバイザリースタッフの役割が大切だと思いますので、活躍の場を広げる活動をこれまで以上に頑張っていいただきたいと思います。 (ryutetsu)
よく言われていることですが、科学的根拠と安全性の情報は公開されても、一般の人々にはハードルが高すぎます。人間が利益やリスクを判断するのに論理的・総合的に判断するには高い負荷がかかるので、一面だけを見るなどヒューリスティック処理によって判断します。つまり機能性表示食品で公開されている情報はほとんどの人は面倒くさくて、見たくないということです。これからアドバイザリースタッフの役割が大切だと思いますので、活躍の場を広げる活動をこれまで以上に頑張っていいただきたいと思います。 (ryutetsu)
![]() アドバイザリースタッフが、科学エビデンスを読み解き、消費者の方に理解しやすい形で、情報提供していくことが、今後より重要になってくるかと思います。
アドバイザリースタッフが、科学エビデンスを読み解き、消費者の方に理解しやすい形で、情報提供していくことが、今後より重要になってくるかと思います。
そのためには、必要に応じて、科学的な根拠になっている論文までさかのぼることも大事かと思います。
また、宣伝広告に謳われていることと、その根拠がいかなるものかも解説できることが、消費者を説得させるうえで必要になってくるかと思います。
個々の品目・成分についても細目に勉強会を開いたほうがよいのであれば、検討いたしますので、リクエストください。
—————————-
![]() 消費者に近い目線でのアドバイザリースタッフ研究会の運営をこれからもよろしくお願いいたします。(あだ)
消費者に近い目線でのアドバイザリースタッフ研究会の運営をこれからもよろしくお願いいたします。(あだ)
![]() 行政、メーカーから提供された情報を、正しく、わかりやすく、消費者に伝えていく(翻訳していく)のが、アドバイザリースタッフの役割と考えます。会員の皆さんが、消費者に説明していく上で、有益な情報をご提供できるようにしていきたいと思います。
行政、メーカーから提供された情報を、正しく、わかりやすく、消費者に伝えていく(翻訳していく)のが、アドバイザリースタッフの役割と考えます。会員の皆さんが、消費者に説明していく上で、有益な情報をご提供できるようにしていきたいと思います。
—————————-
![]() 食品の安全性に真面目に取り組んでください。
食品の安全性に真面目に取り組んでください。
食品添加物を減らすとか、トランス脂肪酸を禁止するとか。(ちゃとたん)
![]() これらの問題に関して、決してないがしろにするわけではありませんが、研究会の取り組むべき問題として考えるとき、もう少し先に取り組むべき課題もあるかと思います。健康食品の正しい情報提供意をしていくことも、広い意味での食品の安全性の問題に取り組む一環と考えております。
これらの問題に関して、決してないがしろにするわけではありませんが、研究会の取り組むべき問題として考えるとき、もう少し先に取り組むべき課題もあるかと思います。健康食品の正しい情報提供意をしていくことも、広い意味での食品の安全性の問題に取り組む一環と考えております。
また、食品添加物等に関しましても、科学的に評価されている資料をみて、正しい情報を提供していきたいと思います。食品に100%安全というものはありません。『シロ』か『クロ』ではなく、すべて量によりそのリスクが変化することも、消費者の皆さんに啓蒙していきたいと考えます。
――――(update 2015.12.4)―――――――――――――――――――――
![]() 東京以外の研修を増やしてほしいです (yuko)
東京以外の研修を増やしてほしいです (yuko)
![]() このご意見は多くの方から頂き、いつも心苦しい思いをしております。
このご意見は多くの方から頂き、いつも心苦しい思いをしております。
毎回の回答になりますが、当研究会は各研修会の参加費で運営しております。そこで問題になるのが、出席者数と、会場費、講師料、印刷費等々の経費の兼ね合いです。残念ながら、赤字となる研修会は、今のところ開催することができません。たとえば、地方の医師会、薬剤師会、栄養士会、あるいは地方自治体等とのタイアップによるなど、経費負担が少ないものが企画できれば、地方でも多くの研修会が可能になると思います。
この辺は、ぜひ会員の皆さんのご協力を頂ければと思います。皆様の所属団体で、なにか企画等があれば、ご紹介いただきたくお願いいたします。
—————————-
![]() 情報提供。情報共有。よろしくお願いします。(そら)
情報提供。情報共有。よろしくお願いします。(そら)
![]() 今後とも、できるだけ早い情報提供に努めてまいります。また、皆さんからのいろいろな情報をお待ちしておりますので、ぜひ、情報提供、ご意見、研修会参加報告、投稿記事等、下記にお送りください。
今後とも、できるだけ早い情報提供に努めてまいります。また、皆さんからのいろいろな情報をお待ちしておりますので、ぜひ、情報提供、ご意見、研修会参加報告、投稿記事等、下記にお送りください。
宛先メールアドレス info@advisory-staff.org
件名 「情報提供」「投稿」など
—————————-
![]() 機能性表示食品を作っている工場の見学、マネジメントシステムを知りたい (きなこ)
機能性表示食品を作っている工場の見学、マネジメントシステムを知りたい (きなこ)
![]() 健康食品の製造工場の見学とGMP解説を組み合わせたものであれば、希望者がある程度集まれば、企画できます。ただ、工場は地方になることが予想されますので、ある程度の交通費の負担が出るかと思います。
健康食品の製造工場の見学とGMP解説を組み合わせたものであれば、希望者がある程度集まれば、企画できます。ただ、工場は地方になることが予想されますので、ある程度の交通費の負担が出るかと思います。
マネジメントシステムというのは、ISOについてのことを言っているのかと思われますが、こちらの方については、当研究会の網羅する内容ではないかと思われます。多くの方が本テーマでの勉強会を希望するようであれば、有料での研修会は可能だと思います。ぜひとも、事務局にご連絡ください。
—————————-
![]() このスタッフの存在が世間にあまり知られていない。機能性表示食品の制度ができたときにどこまで我々が関われるか不安であった。単に企業の製品売上に貢献している制度のように思われる。もっとアドバイザリースタッフ研究会が声を大きくして健康食品に関して情報を発信した方が良いと思う。 (yukababa)
このスタッフの存在が世間にあまり知られていない。機能性表示食品の制度ができたときにどこまで我々が関われるか不安であった。単に企業の製品売上に貢献している制度のように思われる。もっとアドバイザリースタッフ研究会が声を大きくして健康食品に関して情報を発信した方が良いと思う。 (yukababa)
![]() アドバイザリースタッフの認知については、制度のできた当初より言われておりましたが、残念ながら、一般消費者の知るとこにはなっていない現状です。
アドバイザリースタッフの認知については、制度のできた当初より言われておりましたが、残念ながら、一般消費者の知るとこにはなっていない現状です。
各資格認定団体も、市民講座等も開き、一般消費者に少しでも受けいれられるべく努力しているところと思います。
当研究会も、市民公開講座を開きたいのは山々ではありますが、残念ながら、運営費の捻出ができません。
消費者との接点として健康食品相談スタッフの紹介を、当研究会のHPで行っているところです。
アドバイザリースタッフの認知は、資格者の皆さん一人一人の努力によるところが大きいと考えますので、今後とも、積極的にPRいただければと存じます。
—————————-
![]() 機能性表示食品の申請やトクホの申請に関する勉強会を開催して欲しい。(あやめいじゅん)
機能性表示食品の申請やトクホの申請に関する勉強会を開催して欲しい。(あやめいじゅん)
![]() 機能性表示食品の届出、トクホ申請については、どちらかと言うと、当研究会のテーマとしては、少しずれるところもあるかと思いますが、すでに届出られた機能性表示食品の安全性や機能性の根拠に関しての勉強会であれば、希望者があれば企画したいと思いますので、研究会事務局にリクエストください。希望者が多いようであれば、すぐにでも企画いたします。
機能性表示食品の届出、トクホ申請については、どちらかと言うと、当研究会のテーマとしては、少しずれるところもあるかと思いますが、すでに届出られた機能性表示食品の安全性や機能性の根拠に関しての勉強会であれば、希望者があれば企画したいと思いますので、研究会事務局にリクエストください。希望者が多いようであれば、すぐにでも企画いたします。
トクホの申請に関しては、日健栄協が支援していますので、そちらをご活用ください。
http://www.jhnfa.org/index.html
――――(update 2015.11.23)―――――――――――――――――――――
![]() 研修会の充実。知名度をあげる (shochan )
研修会の充実。知名度をあげる (shochan )
![]() 研修会の回数を増やすべく、努力したいと思います。地方でも開催をしたいと思っておりますが、研修会参加費ですべてをまかなっているため、会場費、講師料、通信費、資料印刷費、事務費等を一回毎の研修会参加費でクリアしない限り開催できないのが現実です。
研修会の回数を増やすべく、努力したいと思います。地方でも開催をしたいと思っておりますが、研修会参加費ですべてをまかなっているため、会場費、講師料、通信費、資料印刷費、事務費等を一回毎の研修会参加費でクリアしない限り開催できないのが現実です。
ぜひ、皆さんのご協力を願いたいと思います。
会場の紹介をぜひともお願いいたします。また、地方開催に関して、地方薬剤師会、栄養士会、他の団体との共催もご提案いただければと存じます。
なお、地方で、会員の皆さんが主催して、一般な消費者の方向けの講演会等を実施したいと考えている場合は、研究会事務局にご相談ください。研究会から講師の派遣も行いますので、ご相談ください。
知名度を上げるには、研究会の会員の皆さんの活動が一番だと思います。
ぜひ、機会あるごとに、研究会の会員として活動していることをお伝えいただければと思います。
—————————-
![]() あくまでも中立、公正、かつ科学的根拠を持って情報を提供、消費者へ橋渡しできる役割を果たしてほしい。
あくまでも中立、公正、かつ科学的根拠を持って情報を提供、消費者へ橋渡しできる役割を果たしてほしい。
アドバイザリースタッフのレベル維持、アップのためにも、日進月歩、最新の情報のフォローをしていただけると有難い。 (しまうり)
![]() そのようにできるよう、研究会活動を続けていきますので、今後とも、ご支援ご協力をお願いいたします。
そのようにできるよう、研究会活動を続けていきますので、今後とも、ご支援ご協力をお願いいたします。
また、勉強会や情報提供を通じ、少しでも会員の皆様のお役に立てるように努力したいと思います。
ここで一番問題になるのが、研究会の活動をしていく上での活動費です。
実際、メールマガジンの作成・配信、ブログやHPの更新は、2年間、すべて無償ボランティアで行っており、さすがに厳しい状況になっていることも事実です。
この辺についても、皆様から、ご意見をいただきたいと思います。
ぜひ、お知恵を貸していただければと思います。できれば実現が可能なものをご提案いただきたくお願いいたします。
意見のある方は、12月10日までに、下記に、メールをお願いします。
宛先 info@advisory-staff.org
件名 「研究会の運営に関して」
—————————-
![]() 新しく認可されたり、問題となっている物など、すぐメールで発信お願いしてほしい。(がんちゃん)
新しく認可されたり、問題となっている物など、すぐメールで発信お願いしてほしい。(がんちゃん)
![]() 機能性表示食品、トクホの情報や、健康食品の健康被害情報等は、できるだけ早く皆さんに提供していきたいと考えておりますので、今後とも、ご支援をお願いいたします。
機能性表示食品、トクホの情報や、健康食品の健康被害情報等は、できるだけ早く皆さんに提供していきたいと考えておりますので、今後とも、ご支援をお願いいたします。
ぜひ、皆さんも新しい情報を入手した際には、研究会にご連絡願います。
—————————-
![]() 8月の日本健康科学学会のパネル時にも幾分か提言されておりましたが、4種のアドバイザリースタッフ(以下「AS」)資格そのものは消費者との接点に乏しいことは事実であると思います。医療関係者は、患者と一定の接点がありますが、こと機能性表示食品については、現状「健常人」が対象となる制度なので、健常人と多く接点を持つところに、AS資格者のような有識者の設置が望まれます。
8月の日本健康科学学会のパネル時にも幾分か提言されておりましたが、4種のアドバイザリースタッフ(以下「AS」)資格そのものは消費者との接点に乏しいことは事実であると思います。医療関係者は、患者と一定の接点がありますが、こと機能性表示食品については、現状「健常人」が対象となる制度なので、健常人と多く接点を持つところに、AS資格者のような有識者の設置が望まれます。
私は、現職は健康食品の受託製造業で学術(開発部所属、機能性表示案件担当)が業務ですが、前職ではドラッグストアで医薬品登録販売者/管理栄養士として従事しておりました。やはり消費者に近い店舗販売スタッフ等でも、ASの資格取得を目指せる環境を望みます。(資格取得の敷居の高さを再考) (awa)
![]() 資格認定に関しては、研究会の範囲外のことですので、各団体にお願いするしかありませんが、もし各団体に伝えたいことがあれば、お伝えできますので、遠慮なく申し伝えください。
資格認定に関しては、研究会の範囲外のことですので、各団体にお願いするしかありませんが、もし各団体に伝えたいことがあれば、お伝えできますので、遠慮なく申し伝えください。
ただ、一番大事なのは、自分の所属している団体に、自分の意見として、直接認定団体に伝えることが大事かと思います。
機能性表示食品は、トクホでも行われていない、各種の製品の情報が公開されています。消費者も見ることはできますが、中々ハードルが高いかと思います。消費者が購入する場所に、AS資格者がいて説明できるような環境ができることを望みたいと思います。
そのような、資格者を置く薬店等が増えることを期待したいと思います。
現在、ドラックチェーン協会も、機能性表示食品に関して、何らかのシステムを構築する準備を進めていると聞いております。そこに、AS資格者が関与できるような形がとられることを願いたいと思います。
—————————-
![]() 機能性表示食品として届出が)受理された案件について事例説明、検討会など(かわ)
機能性表示食品として届出が)受理された案件について事例説明、検討会など(かわ)
![]() 定期の研修会で、個々の品目について取り上げるは、どうかと思いますので、別の勉強会を企画し、ディスカッション形式の、勉強しませんか?
定期の研修会で、個々の品目について取り上げるは、どうかと思いますので、別の勉強会を企画し、ディスカッション形式の、勉強しませんか?
都内でしたら、会場費だけの負担を、参加者の人数割でも良いなら、企画いたします。
地方でも人数が集まれば、開催は可能だと思います。その場合、コーディネーターの交通費は、参加者の方で負担していただく形でお願いさせていただくと思います。
この件については、意見を求めますので、意見のある方は、12月10日までに、下記に、メールください。
宛先 info@advisory-staff.org
件名 「勉強会の件」
参加したいという人が多いようでしたら、すぐにでも企画したいと思います。
—————————-
![]() やはり、薬との関係の調べ、調査のデータが欲しいのと、堀みちこ先生のような方々を呼んで、いろいろ、講習会を開いていただきたく思います。 (石ちゃん)
やはり、薬との関係の調べ、調査のデータが欲しいのと、堀みちこ先生のような方々を呼んで、いろいろ、講習会を開いていただきたく思います。 (石ちゃん)
![]() 健康食品と医薬品の相互作用に関する資料に関しては、会員の皆様も情報収集に苦労されていると思います。
健康食品と医薬品の相互作用に関する資料に関しては、会員の皆様も情報収集に苦労されていると思います。
今後、機能性表示食品制度が充実することにより、医薬品との相互作用や、健康食品による健康被害情報が収集され、公表されていくことに期待したいものです。
参考となるデータベース
城西大学薬学部 食品‐医薬品相互作用データベース
国立健康・栄養研究所 「健康食品」有効性・安全性情報データベース
研修会の講師については、色々な先生のお話が聞けるように、検討していきたいと思います。
来春も、全国数会場にて研修会を実施の予定をしております。
—————————-
![]() 機能性表示について勉強会を行ったり、日本臨床栄養協会の総会の中でシンポジウムを開いたり、業界団体のように「機能性表示の有るべき姿・情報伝達のあり方について」声明を発表したりすることを企画すべき。せっかく日本臨床栄養協会とのつながりがあるのだから、それを生かしてほしい。 (kazu)
機能性表示について勉強会を行ったり、日本臨床栄養協会の総会の中でシンポジウムを開いたり、業界団体のように「機能性表示の有るべき姿・情報伝達のあり方について」声明を発表したりすることを企画すべき。せっかく日本臨床栄養協会とのつながりがあるのだから、それを生かしてほしい。 (kazu)
![]() 研究会活動の幅を広げていきたいと思います。研究会活動は、会員の方が積極的に参加していただくことに意義があると考えておりますので、ぜひ、活動内容の提案だけではなく、率先して研究会活動に参加いただきたくご協力願います。
研究会活動の幅を広げていきたいと思います。研究会活動は、会員の方が積極的に参加していただくことに意義があると考えておりますので、ぜひ、活動内容の提案だけではなく、率先して研究会活動に参加いただきたくご協力願います。
他団体との協力についても、積極的に取り組んでいきたいと考えています。
他団体の学会でのシンポジウム等の開催につきましては、予算面等も考慮し検討していきたいと思います。当研究会は会費無料で運営しているため、中々活動の幅を広げられないことがあることもご理解いただければ幸いです。
—————————-
![]() いつも取りまとめていただいてありがとうございます。 (みに)
いつも取りまとめていただいてありがとうございます。 (みに)
![]() 応援、ありがとうございます。会員の皆様に、少しでも多くの情報を提供できるよう、今後も活動していきます。
応援、ありがとうございます。会員の皆様に、少しでも多くの情報を提供できるよう、今後も活動していきます。
—————————-
![]() 会員費が高い、研修数などは問題ないが単位が取りづらい、フォローが少ない。もう少し温かみがあっても良いと思います。 (Akky)
会員費が高い、研修数などは問題ないが単位が取りづらい、フォローが少ない。もう少し温かみがあっても良いと思います。 (Akky)
![]() たぶん、他の団体と勘違いしてのコメントかと思います。
たぶん、他の団体と勘違いしてのコメントかと思います。
当研究会は、会費無料にて運営しております。研修会については、最低限の参加費を徴収させていただいております。事務作業等はすべてボランティアにより運営しております。
—————————-
![]() 今まで通り、定期的な情報発信を継続していただければありがたいです。 (すがちゃん)
今まで通り、定期的な情報発信を継続していただければありがたいです。 (すがちゃん)
![]() 応援ありがとうございます。
応援ありがとうございます。
今後とも、メルマガ、ブログ、HP等で、情報発信していきますので、ご協力のほどお願いいたします。
会員の皆様からの投稿、情報提供もいただければ、より充実した研究会活動になっていくと考えますので、積極的な参加をお願いいたします。
—————————-